ブランディングは経営そのもの ― 良い商品を“選ばれる商品”に変えるには?
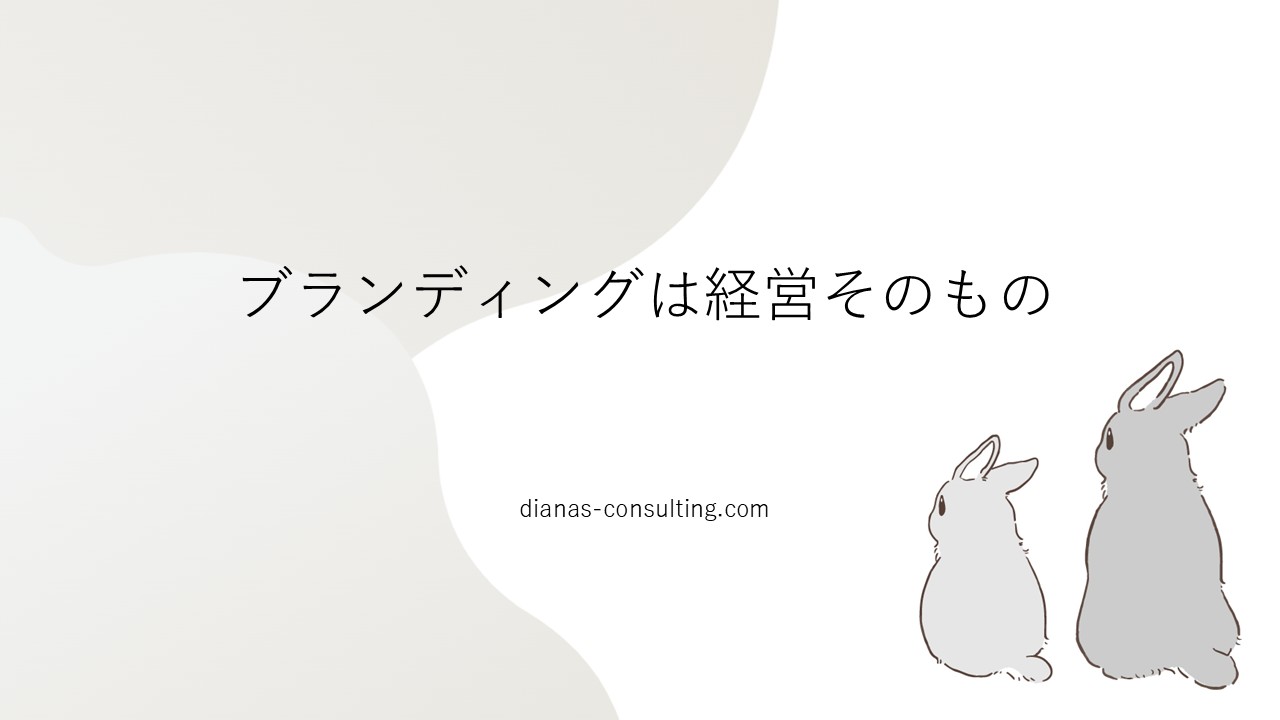
診断士の視点 ― ブランディングは経営そのもの
「良い商品なのに売れない」――これは私が中小企業診断士として現場で耳にする典型的な悩みです。
経営者は自社の商品やサービスに強い自信を持っています。しかし、それが顧客に“選ばれる理由”として伝わらなければ、成果にはつながりません。
多くの方は「ブランド=ロゴやデザイン」と考えがちですが、実際にはブランドとは経営そのものの表れです。事業計画、財務、組織、人材、販路――これら経営資源のすべてが一貫して顧客にどう映るか、それがブランドを形づくります。
本稿では、中小企業診断士として数多くの経営支援を行ってきた立場から、良い商品を“選ばれる商品”へと変えるためのポイントを解説します。
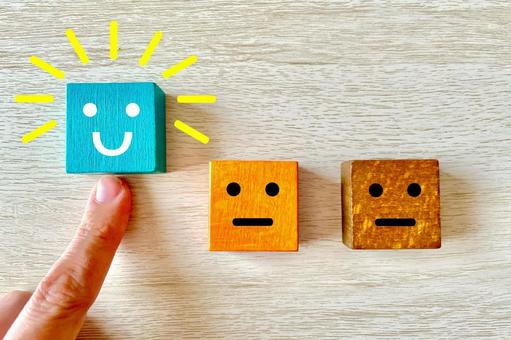
良い商品を“選ばれる商品”に変えるには?
市場が成熟した今、顧客が評価するのは単なる「品質」ではなく「体験」や「信頼」です。
商品力が高いことは前提条件にすぎません。
診断士の支援現場でも、経営者が「うちは技術力が強みだ」と語る企業ほど、顧客にとっての価値が言語化されていないケースが目立ちます。結果として、競合との差別化が伝わらず、価格競争に巻き込まれがちです。
良い商品を“選ばれる商品”にするためには、その強みを顧客目線で「選ばれる理由」に翻訳し、発信・体験設計に組み込む必要があります。
ブランドの本質は「経営計画との一体化」
ブランドは広告の後付けではなく、経営計画に組み込むべき戦略要素 です。
診断士が事業計画の策定を支援する際には、売上や利益と同時に「どの顧客に、どんな価値を、どう感じて頂くか」というブランド設計を必ず意識します。(ポイントは、価値をどう届けるかではなく、どう感じて頂くか、にこだわることです)
ブランドは、財務や人材戦略と切り離して考えるものではありません。
むしろ、それらを結びつけることで、企業は長期的に選ばれる力を手にします。ブランドを考えることは、経営の未来を設計することにほかなりません。
ケース:A社のブランド再設計
地方の食品メーカーA社は、伝統製法による高品質な商品を持っていましたが、「美味しい」という表現だけでは他社との差別化にならず、伸び悩んでいました。
経営計画にブランドの視点を取り入れ、「家族の食卓に安心を届ける」というメッセージを打ち出したことで状況が変わります。製造工程や地域性をストーリーとして発信するようになり、顧客の共感を獲得。結果として、販売チャネルの広がりやEC売上の増加につながりました。
この事例が示すのは、ブランドは広告やキャンペーンではなく、経営全体に組み込むことで初めて効果を発揮する ということです。
診断士からの提言 ― 選ばれる企業への第一歩
ブランドは未来をつくる投資でもあります。
第一歩は、「自社が選ばれる理由」を事業計画の中で明文化することです。売上目標や投資計画と同じレベルで、ブランドの方向性を数値や言葉に落とし込み、社内外で共有することが、持続的成長の基盤になります。
これは単なるマーケティング施策ではなく、事業計画や財務戦略と一貫したブランド経営の出発点です。
診断士として断言できるのは、ブランドを経営計画に組み込んだ企業ほど、持続的な成長と安定した資金調達につながっているという事実です。
まとめ ― ブランドは経営そのもの
ブランドは、顧客の目に映る「経営そのもの」です。
どれほど良い商品を持っていても、価値として伝わらなければ選ばれ続けることはできません。
ぜひ、自社のブランドを広告の一要素としてではなく、経営戦略の中心に据えてください。
それこそが、診断士が見てきた「選ばれ続ける企業」の共通点であり、Bright Companyへの第一歩となります。


